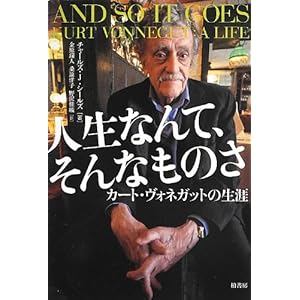大雨の後、ようやく一息つける温度になったけど、この夏はホント暑かったなあ。SF大会以来、暑すぎてどこにも行かず、何もせずだったような気がする。
 大森望が褒めていたのでちょっと気になっていた近本洋一『愛の徴 天国の方角』は、メフィスト賞受賞作ということで、昔SFという触れ込みで非道いのを読まされた記憶があり、なかなか読む気が起こらなかったけれど、眉に唾付けて読んだ。本自体は全ページに透かしと柱を印刷したなかなか凝った造り。もう少し面積を取ってやった方がよかったかも。
大森望が褒めていたのでちょっと気になっていた近本洋一『愛の徴 天国の方角』は、メフィスト賞受賞作ということで、昔SFという触れ込みで非道いのを読まされた記憶があり、なかなか読む気が起こらなかったけれど、眉に唾付けて読んだ。本自体は全ページに透かしと柱を印刷したなかなか凝った造り。もう少し面積を取ってやった方がよかったかも。
話の方はかなり念入りに考えられた量子コンピュータSFとファンタジイのアマルガム。ヴェラスケスの妻になった魔女(まだ荒蕪地だったヴェルサイユにあったお屋敷に下女として仕えた孤児)の物語/ファンタジーと量子コンピュータにヴェラスケスが活躍した時代のブルボン朝フランスの古文書を大量に喰わせたことで何が出力されているのか推理する研究所員の物語/SFミステリ?がそれ。それは本の扉ページにあるヴェラスケスの『鏡のヴィーナス』から紡がれた物語のように作ってある。読んでいる分には十分面白いし、長谷敏司『あなたのための物語』を思いっきり陽性にしたともいえる。ただこれだけの長さを使って受け取る物語の重みは少ない。帯に推薦の言葉を寄せている冲方丁の『光圀伝』ほどの手応えがない。それはたとえばファンタジイの始まりの手続きの軽さや悩んでいる量子コンピュータの使用率が100パーセントになったときのイメージがまるでエヴァンゲリオンのそれみたいだったりということが影響している。新人の書きものとしては驚くべき出来映えとはいえ、分厚い新書版で読んだ方が印象的ではなかろうか。と、思っていたら本当に新書版になって出ていた。ちぇっ。
 本家クラークとは懸け離れたタイプの作品が選ばれるアーサー・C・クラーク賞だけれど、これはいくらなんでもだよなあと思わせたのが、ジェイン・ロジャーズ『世界を変える日に』。これは論理自体が間違っているのに、それを感動作にできるとおもった作家の作品だ。帯にあるようなまともな作品と類似した設定を使えばという勘違いの下に話がつくりあげられている。出産が死に繋がる設定で周囲(父親)の意見を振り切って出産に至るまでを少女が1人称的に物語るが、それは自由意志という名の下に自爆テロリストに仕立て上げられる子どもの物語として読めてしまう。ストーリー自体も早くから手の内を晒したまま何のひねりもなく書いていて、それがエンターテインメントではないシリアスな物語だと思いこんでいることにウンザリさせられる。クラーク賞の審査員は目が節穴か。
本家クラークとは懸け離れたタイプの作品が選ばれるアーサー・C・クラーク賞だけれど、これはいくらなんでもだよなあと思わせたのが、ジェイン・ロジャーズ『世界を変える日に』。これは論理自体が間違っているのに、それを感動作にできるとおもった作家の作品だ。帯にあるようなまともな作品と類似した設定を使えばという勘違いの下に話がつくりあげられている。出産が死に繋がる設定で周囲(父親)の意見を振り切って出産に至るまでを少女が1人称的に物語るが、それは自由意志という名の下に自爆テロリストに仕立て上げられる子どもの物語として読めてしまう。ストーリー自体も早くから手の内を晒したまま何のひねりもなく書いていて、それがエンターテインメントではないシリアスな物語だと思いこんでいることにウンザリさせられる。クラーク賞の審査員は目が節穴か。
 絶好調の中村融の埋もれた翻訳/未訳SF復活アンソロジイ・シリーズ第4弾中村融編『時を生きる種族』は、今回もなかなか楽しめる。臆面もない願望充足SFのヤングはそれはそれで嬉しいし、「宇宙にたそがれが訪れた」という出だしがいかにものムアコックは話の筋をすぐ忘れるけど良い作品だ。ディ・キャンプ、シルヴァーバーグ、ライバー、クリンガーマンと50年代アメリカSFの雰囲気をよく伝える作品が単純といえば単純だけれど素晴らしい。そして35年ぶりに読んだT・L・シャーレッド「努力」。40年代SFだったなんて。戦争が終わってまだ2年というあの時代に戦勝国アメリカにおいてこのアイデアでシリアスな反戦SFが書けたなんて、しかもアナログ誌だなんて感動して当たり前だよねえ。
絶好調の中村融の埋もれた翻訳/未訳SF復活アンソロジイ・シリーズ第4弾中村融編『時を生きる種族』は、今回もなかなか楽しめる。臆面もない願望充足SFのヤングはそれはそれで嬉しいし、「宇宙にたそがれが訪れた」という出だしがいかにものムアコックは話の筋をすぐ忘れるけど良い作品だ。ディ・キャンプ、シルヴァーバーグ、ライバー、クリンガーマンと50年代アメリカSFの雰囲気をよく伝える作品が単純といえば単純だけれど素晴らしい。そして35年ぶりに読んだT・L・シャーレッド「努力」。40年代SFだったなんて。戦争が終わってまだ2年というあの時代に戦勝国アメリカにおいてこのアイデアでシリアスな反戦SFが書けたなんて、しかもアナログ誌だなんて感動して当たり前だよねえ。
 余りの暑さに、トイレで消夏本をと思い、しばらく積ん読状態だった会津信吾・藤元直樹編『怪樹の腕 〈ウィアード・テールズ〉戦前邦訳傑作選』を読み始めた。1、2編読む内にトイレの用は終わるのだが、涼しくはならない。ま、ホラー不感症なので仕方がないけれど。でもとりあえずスイスイ読めるし、各編に付けた会津信吾の文章がなかなか面白い。20年前だとこれだけの情報を集めるのに膨大な労力を必要としただろう。こういうトリビアをある程度まとめる上でも現代の情報網は威力を発揮する(ただし、求めるものだけに対してね)。藤元さんの《ノット・アット・ナイト》探索は、いかにも藤元さんらしい書きっぷりで愉しく読ましてもらいました。遅くなりましたが、出版おめでとうございます。
余りの暑さに、トイレで消夏本をと思い、しばらく積ん読状態だった会津信吾・藤元直樹編『怪樹の腕 〈ウィアード・テールズ〉戦前邦訳傑作選』を読み始めた。1、2編読む内にトイレの用は終わるのだが、涼しくはならない。ま、ホラー不感症なので仕方がないけれど。でもとりあえずスイスイ読めるし、各編に付けた会津信吾の文章がなかなか面白い。20年前だとこれだけの情報を集めるのに膨大な労力を必要としただろう。こういうトリビアをある程度まとめる上でも現代の情報網は威力を発揮する(ただし、求めるものだけに対してね)。藤元さんの《ノット・アット・ナイト》探索は、いかにも藤元さんらしい書きっぷりで愉しく読ましてもらいました。遅くなりましたが、出版おめでとうございます。
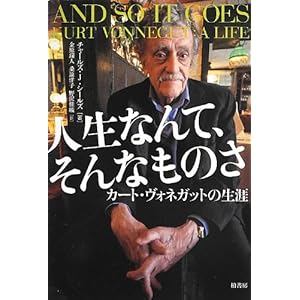 おお、ヴォネガットの伝記が。ということで早速読んでみたチャールズ・シールズ『人生なんて、そんなものさ カート・ヴォネガットの生涯』は、タイトルが「そういうものだ」じゃない時点で不安を覚えたが、その予感は残念ながら当たってしまった。この厚さにふさわしいヴォネガットの人生情報が満載だが、読んでいて面白くない。この作者はヴォネガットの作品が嫌いなんじゃないかと思われるくらいヴォネガットの暗い人生のトリビアを積み重ねる。これからもヴォネガット論はたくさん書かれるだろうし、そうなりゃオレが最初の詳しい伝記を書いておけば、どいつもこいつもオレを無視して書けるわけがないし、こりゃ押さえておかなきゃなあ、と考えたんじゃなかろうか、シールズさんは。まあ、スタージョンとの出会いだけは、その書き方に暖かみはないけれど、面白い。今思うと、ブラッドベリの自伝は幸福な読み物だったなあ。
おお、ヴォネガットの伝記が。ということで早速読んでみたチャールズ・シールズ『人生なんて、そんなものさ カート・ヴォネガットの生涯』は、タイトルが「そういうものだ」じゃない時点で不安を覚えたが、その予感は残念ながら当たってしまった。この厚さにふさわしいヴォネガットの人生情報が満載だが、読んでいて面白くない。この作者はヴォネガットの作品が嫌いなんじゃないかと思われるくらいヴォネガットの暗い人生のトリビアを積み重ねる。これからもヴォネガット論はたくさん書かれるだろうし、そうなりゃオレが最初の詳しい伝記を書いておけば、どいつもこいつもオレを無視して書けるわけがないし、こりゃ押さえておかなきゃなあ、と考えたんじゃなかろうか、シールズさんは。まあ、スタージョンとの出会いだけは、その書き方に暖かみはないけれど、面白い。今思うと、ブラッドベリの自伝は幸福な読み物だったなあ。
 いわゆる冬の時代の日本SF短編を集めた日本SF作家クラブ編『日本SF短編50 Volum4』は、読みやすい作品が揃ったアンソロジイ。最初の3編がジャンル外作家(SF作家クラブ員だけど)ということ自体、当時のジャンルSFの状況が思いやられる。宮部みゆきは、日常の雰囲気の描出が非常に上手く、その分非日常へと移行するとちょっと違和感が生じる。篠田節子は少し書き方を変えれば、筒井康隆的な神経症的スラップスティックだけれど、ちゃんと落ち着く。この3人で200ページを超えるので、後はやや短めの作品が続く。藤田雅矢の作品は「計算草」というアイデアと田舎の少年少女の恋を上品に描く。菅浩江は王道のアイデアSFでオチも上手い。小林泰三は言わずもがなだし、牧野修は本格的に神経症な言語世界を構築。田中啓史は再読不能なので、パス。これを「不快な傑作」というのは言葉の誤用だ。藤崎愼吾も北野勇作も再読だけれど、初読と同じ。藤崎愼吾はなかなかの作品。亀話は読んでいる内に思い出してきたので、いい話だ。
いわゆる冬の時代の日本SF短編を集めた日本SF作家クラブ編『日本SF短編50 Volum4』は、読みやすい作品が揃ったアンソロジイ。最初の3編がジャンル外作家(SF作家クラブ員だけど)ということ自体、当時のジャンルSFの状況が思いやられる。宮部みゆきは、日常の雰囲気の描出が非常に上手く、その分非日常へと移行するとちょっと違和感が生じる。篠田節子は少し書き方を変えれば、筒井康隆的な神経症的スラップスティックだけれど、ちゃんと落ち着く。この3人で200ページを超えるので、後はやや短めの作品が続く。藤田雅矢の作品は「計算草」というアイデアと田舎の少年少女の恋を上品に描く。菅浩江は王道のアイデアSFでオチも上手い。小林泰三は言わずもがなだし、牧野修は本格的に神経症な言語世界を構築。田中啓史は再読不能なので、パス。これを「不快な傑作」というのは言葉の誤用だ。藤崎愼吾も北野勇作も再読だけれど、初読と同じ。藤崎愼吾はなかなかの作品。亀話は読んでいる内に思い出してきたので、いい話だ。
期待して読んだら肩すかしを食らったチャイナ・ミエヴィル『クラーケン』上・下。『都市と都市』と『言語都市』を書いている最中の息抜きといわれれば、そんな感じもする。 博物館のダイオウイカ標本が容器ごと消失。そこから巻き起こる裏ロンドンのオカルト宗教・魔法世界のテンヤワンヤだけで延々と話が続く。読んでてちっともノレないのが辛い。個々には魅力的な設定やキャラが目一杯揃えられているのだけれど、ミエヴィルは複雑骨折系の騙りを採用しているので、オフビートでさえないノリの悪さ。それでも処女作『キング・ラット』や裏ロンドンファンタジイ『アン・ラン・ダン』やミエヴィル作品じゃないけど『ネヴァーウェア』に出てくる2人組の殺し屋などを彷彿とさせて、まあ面白いんだろうなという感触だけが残る残念な1作。
 SFを離れると、柴田元幸『代表質問 16のインタビュー』が出たので読んでみた。柴田元幸のファンではないので、たまに読むだけだけれど、この本の目玉はなんといっても村上春樹と村上春樹論を書いた内田樹へのインタビュー。どっちも他人が要らない点で共通しているが、威張り屋内田樹にヘコヘコしながら(という設定)、人生相談するインタビュアーが可笑しい。その点、村上春樹は全く不透明でさっぱりわからない。翻訳者同士の対談は読みやすくてよいけど、やはり異種格闘技の方が面白いよね。
SFを離れると、柴田元幸『代表質問 16のインタビュー』が出たので読んでみた。柴田元幸のファンではないので、たまに読むだけだけれど、この本の目玉はなんといっても村上春樹と村上春樹論を書いた内田樹へのインタビュー。どっちも他人が要らない点で共通しているが、威張り屋内田樹にヘコヘコしながら(という設定)、人生相談するインタビュアーが可笑しい。その点、村上春樹は全く不透明でさっぱりわからない。翻訳者同士の対談は読みやすくてよいけど、やはり異種格闘技の方が面白いよね。
 終戦の8月ということで文庫になった前間孝則『技術者たちの敗戦』は機械技術系ノンフィクションを書き続けている作者の取材こぼれ話的1冊。前間さんには以前お世話になって面識があるので、できるだけ読むようにしているのだけれど、この夏に出た最新作にはまだ手が出ない。こちらは2004年作品の文庫化。今話題の堀越二郎、新幹線の島秀雄、戦後巨大タンカーを造り続けて造船王国日本を牽引した真藤恒、戦時中のレーダー開発を担った緒方研二、戦時中日本初のジェットエンジンを開発し、戦後はホンダでF1開発を指導して優勝させた中村良夫の5人を取り上げて、彼らの言葉を紹介しながら戦前戦時中の優秀な技術者の思想や行動や信念を浮き彫りにする。この5人のなかでは堀越二郎だけ、前間さんが著述活動に入る前に亡くなっているので、記録と周辺人物へのインタビューを中心に構成されている。これらの技術者はある意味スーパーエンジニアだが、誰もが戦争の中で技術者の道を歩んだ人々でもある。これらの人物の歩みから時代の中の技術者像、あの時代を経たある意味強靱な精神が浮き彫りになっている。前間さんは後書きでこれらのスーパーエンジニアたちの実像を神話化される前に書き残しておきたかったとしておられるが、やはり神話化は進んでしまうんだろうなと思われます。
終戦の8月ということで文庫になった前間孝則『技術者たちの敗戦』は機械技術系ノンフィクションを書き続けている作者の取材こぼれ話的1冊。前間さんには以前お世話になって面識があるので、できるだけ読むようにしているのだけれど、この夏に出た最新作にはまだ手が出ない。こちらは2004年作品の文庫化。今話題の堀越二郎、新幹線の島秀雄、戦後巨大タンカーを造り続けて造船王国日本を牽引した真藤恒、戦時中のレーダー開発を担った緒方研二、戦時中日本初のジェットエンジンを開発し、戦後はホンダでF1開発を指導して優勝させた中村良夫の5人を取り上げて、彼らの言葉を紹介しながら戦前戦時中の優秀な技術者の思想や行動や信念を浮き彫りにする。この5人のなかでは堀越二郎だけ、前間さんが著述活動に入る前に亡くなっているので、記録と周辺人物へのインタビューを中心に構成されている。これらの技術者はある意味スーパーエンジニアだが、誰もが戦争の中で技術者の道を歩んだ人々でもある。これらの人物の歩みから時代の中の技術者像、あの時代を経たある意味強靱な精神が浮き彫りになっている。前間さんは後書きでこれらのスーパーエンジニアたちの実像を神話化される前に書き残しておきたかったとしておられるが、やはり神話化は進んでしまうんだろうなと思われます。
 前から気になっていた白井聡『永続敗戦論 戦後日本の核心』をパラパラしたら、止まらなくなって一気読み。多分書いた方も一気に書き上げたと見えて、勢いが良い。
前から気になっていた白井聡『永続敗戦論 戦後日本の核心』をパラパラしたら、止まらなくなって一気読み。多分書いた方も一気に書き上げたと見えて、勢いが良い。
米国にすり寄りながらもしくは米国の意向に従いながら、表向きは米国に与えられた憲法を「改正」することが国家的意思であるかのようにふるまう日本の政権は、中国の存在が前面化するにつれ、最終的にサンフランシスコ条約無視やポツダム宣言違背に踏み込むことによって対米関係破綻の危機に進まざるを得ないと喝破するその論理は実に明解だ。戦前戦時中の「国体」の定義を「犠牲のシステム」とした片山杜秀を引きながら、また豊下楢彦による戦後占領下の日米関係の研究を引きながら、戦後失われた「犠牲のシステム」がアメリカの占領政策と昭和天皇の意向のもと「国体」を「永続敗戦」と同義にすることで「護持」したとする論理は、本書をスイスイと読んでる限りでは納得させるだけの勢いがある。片山杜秀同様、政治哲学や政治思想史を専門とする著者は1977年生まれとまだ30代前半だが、いわゆる「虚妄の戦後」のよって来たる所を見事に解き明かして見せたといえる。著者は基本的に右も左も切って捨てているが、現体制否定という意味では極左に見えるかもしれない。「永続敗戦」はあまり見栄えが良くないので定着はしないだろうが、その内容は十分なパワーがある。あとがきで個人に戻っちゃうところが真摯だけどちょっと弱い。
THATTA 304号へ戻る
トップページへ戻る
 大森望が褒めていたのでちょっと気になっていた近本洋一『愛の徴 天国の方角』は、メフィスト賞受賞作ということで、昔SFという触れ込みで非道いのを読まされた記憶があり、なかなか読む気が起こらなかったけれど、眉に唾付けて読んだ。本自体は全ページに透かしと柱を印刷したなかなか凝った造り。もう少し面積を取ってやった方がよかったかも。
大森望が褒めていたのでちょっと気になっていた近本洋一『愛の徴 天国の方角』は、メフィスト賞受賞作ということで、昔SFという触れ込みで非道いのを読まされた記憶があり、なかなか読む気が起こらなかったけれど、眉に唾付けて読んだ。本自体は全ページに透かしと柱を印刷したなかなか凝った造り。もう少し面積を取ってやった方がよかったかも。