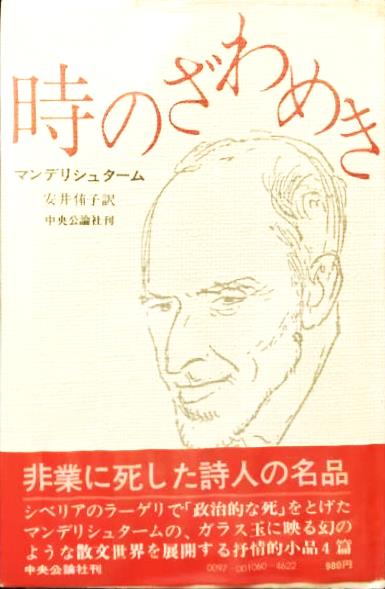ここで自分の書いたものを読み返すと、意味不明な日本語になっていることがよくわかる。われながら情けないのではあるけれど、年齢と共にミスタッチは殖えるし、コピペとかしているうちに忘れてしまうこともあるので、余程時間をおいて見直さないと意味不明な日本語を排除するのは難しい。さすがに人前でしゃべるときのレジュメは何回も読み返すけれど、この文章は勢いで書いてるからなあ。読んで下さる方(特に主宰の大野万紀さん)には申し訳ないが、そんなものだと思っておいて下さい。
地元のオンボロ映画館では、遅ればせながら話題作はそれなりに上映してくれる。今回見に行ったのは、インド映画『RRR』と庵野秀明監督『シン仮面ライダー』の2作。
『RRR』は評判通りの面白さで、久しぶりに見るエンターテインメント大作(見た目『エブエブ』よりもずっと金〔人件費〕がかかっている)。まあ3時間以上あって、これでもかこれでもかとアクションと歌と踊りがテンコ盛り。それでいてストーリーは、1920年代大英帝国の苛酷な支配下にあるインドを救うためマッチョな男2人が大活躍する話なんだから、スゴいとしか云いようがない。イギリスが徹底的にコケにされているのを見て、イギリスでの評価は、と見るとけっこう評価が高い。しかし、これを見終わって思ったことは、中国や韓国(朝鮮)を舞台に、大日本帝国を歌と踊りとアクションでコケにする映画が作られる日は来るのだろうか(実はもうある?)、だった。
一方、『シン仮面ライダー』の方は、テレビ番組が始まった当時既に高校生だったのでまったく見ていないこともあり、ほとんど思い入れがないため、見ながら思ったことは「コレは面白いんだろうか」というものだった。
『仮面ライダー』をテレビで全話見たのは、35年近く前、子供がまだ幼稚園児だった頃の『仮面ライダーBlack』とその続編RXだけである。その時思ったのは、石森章太郎のコスチュームデザインセンスがいかに優れていたかということで、もちろんその当時の番組に参加したコスチュームデザイナーの洗練が加わっていたけれど、原型のオリジナリティは明らかだった。その点は、庵野監督も石ノ森章太郎に十分敬意を払っているように思えた。
しかし、視覚的効果はともかくとして、話の方がとても判りにくい、というかいつもの庵野ワールドが展開していて、それは脇を固めた前作でお馴染みの俳優たちやこの監督が持つ「正義」と「世界」への違和感から感じられるものである。要はエンターテインメント性が複雑骨折しているような感覚なのだ。そりゃ、難しすぎるよ。
どうもSFプロパーな作品の発刊日が月末に集中しているせいで、最近は毎回締め切り後になるとに読みたい新刊プロパーSFがないと云うことになっているような気がする。まあ、当方の趣味が狭すぎるということが原因なんだけれど。
 冒頭に斜線堂有紀、巻末に深緑野分が入っていたので、手を出したものの斜線堂有紀がぜんぜんSFじゃなかったので積ん読にしたのが、『百合小説コレクション Wiz』河出文庫2月刊。だったたけれど、気を取り直して読んでみた。収録作家は他に、アサウラ・小野繙・櫛木理宇・坂崎かおる・南木義隆・宮木あや子。
冒頭に斜線堂有紀、巻末に深緑野分が入っていたので、手を出したものの斜線堂有紀がぜんぜんSFじゃなかったので積ん読にしたのが、『百合小説コレクション Wiz』河出文庫2月刊。だったたけれど、気を取り直して読んでみた。収録作家は他に、アサウラ・小野繙・櫛木理宇・坂崎かおる・南木義隆・宮木あや子。
百合小説は好きですか、と訊かれれば、いいえ、と答えると思うが、最近の作家たちの作品には、男女問わずまたエンターテインメント的ジャンルに限らず百合モノが繁茂しているので、まあ仕方が無い。
その斜線堂有紀「選挙に絶対行きたくない 家のソファーで食べて寝て映画見たい」(って、なんちゅうタイトル。けど、なろう系のタイトルからすればどうってこともないか)は、いわゆる頭が涼しい系のズボラな高学歴女子が語る、可愛いけれど低学歴を気にしながらLGBTの権利擁護に熱心な女子に振り回される話。タイトルはそれ自体、男社会の無自覚な抑圧を表している。この作者の得意技であるハードなホラーを離れた、それなりに幸せな1作。面白く読めるし、ズボラな女でいたいのに頭が良いだけでなんで珍重されなきゃいけないのかとか、お説御尤もだけれど、当方向きではないよねえ。
小野繙(ひもとく)「あの日、私たちはバスに乗った」は、「ユアは子どもを産んだ。十歳の頃だった。」という強烈なフックで始まるが、実際は小学生から女子高生までの時代の紆余曲折の果て、ハッピーエンドを迎える少女たちの話。タイトルは末尾の一文。なお、ユアは視点人物の想い人となる女の子。出だしの一文はSFを期待させるけど、もちろん違います。作者は96年生まれで、実質コレがプロデビュー作。
櫛木理宇「パンと蜜月」は、既婚だが夫が迎え入れた女との愛の生活に没頭する妻の話。ウーン、設定のお陰で面白くは読めますが・・・。扉ページ裏の、好きな「百合作品」アンケートの答えが、高口里純『花のあすか組!』。これぐらい昔の作品だと当方も読んでました。
タイトルから内容がサッパリ分からない宮木あや子「エリアンタス・ロバートソン」は、作中ジョナサン・ベイカーという高名なクラシック・ピアニストが連弾の相方として連れてきた女性の方名前だった(もちろん当方はそんなピアニストはどちらも聞/聴いたことがない)。語り手は恋する女性のために狂気の域に達した経験を持つ。そして語り手がお嬢様学校での教師時代に、偶然受け持ったエキセントリックな二人の女生徒の片方がそのピアニストの名前だった。そして彼女の楽屋を訪れて知ったことは・・・。二重の百合モノ。
アサウラ「悪い奴」は、百合と殺人(未遂)と騙りの3点セットで、ちょっとマンガっぽいというか、ラノベっぽい造りの1作。いまどきのエンターテインメントかな。
坂崎かおる「嘘つき姫」は、第2次世界大戦中に「嘘つき」母親に育てられながら、戦禍で焼け出され、その母が戦災孤児の少女を引き取ったところで母が死亡、引き取った少女と共に戦災孤児として施設に入れられた語り手の少女が虚実が入り交じったその後を物語る・・・。これは深緑野分を髣髴とさせる語り/騙りで大変面白く読める1作。やはりSF成分が強い作家に親しみを感じる。
南木義隆「魔術師の恋その他の物語」も、デビュー長編は当方の関心の外としたわりには、けっこう楽しめる「悪魔の契約」ものの百合版バリエーション。と思ったら、最後まで読んでも「悪魔の契約」が何のフックにもなってないといういい加減さ。ま、語り手がハッピーなら、それでいいのか。
深緑野分「運命」は、いわゆるメタ・フィクションだが、メタメタ・フィクションといった方が良いかもな小品。ワハハハ。
ということで、SFでなくても面白いものは面白いが、SFだともっと嬉しいということです。
 『真藤順丈リクエスト! 絶滅のアンソロジー』は、以前読んだ『森見登美彦リクエスト! 美女と竹林アンソロジー』と同じ「小説宝石」に掲載された短篇を集めたアンソロジー・シリーズの1冊。親本は2021年8月刊で、昨年9月に文庫化されたもの。積ん読になりつつあったけれど、読んでみた。
『真藤順丈リクエスト! 絶滅のアンソロジー』は、以前読んだ『森見登美彦リクエスト! 美女と竹林アンソロジー』と同じ「小説宝石」に掲載された短篇を集めたアンソロジー・シリーズの1冊。親本は2021年8月刊で、昨年9月に文庫化されたもの。積ん読になりつつあったけれど、読んでみた。
文庫版あとがきで編者はロシアのウクライナ侵攻に言及しているが、それ以来現在でも相変わらず驚くべき事態が進行している最中なのに、感覚的には毎日のニュース化してしまっている。同じ刺激を受けていると無感覚になるのは、ウェーバーの法則だったっけ。それはともかく、収録作品については編者自らが熱烈解説を書いているので、興味のある方は立ち読みして下さい(って、もう店頭にないか)。
佐藤究「超新星爆発主義者」は、話題になった短編集には入っていないようだ。アメリカのテロ対策がSF的スケールで実行される話。ただの現実的なストーリーでもある。
東山彰良「絶滅の誕生」は、架空の創世記譚。筒井康隆よりも雑ぱくなパロディになっている。
河崎秋子「梁が落ちる」は、目が覚めてアパートの窓を開けたら向かいのビルを囲った足場が一面崩れていた・・・、と云うところから始まる感覚的な現実変容譚。いわゆる実存的ホラーっていうタイプかな。
王谷晶「○○しないと出られない部屋」は、最初の段落の末尾に「ここは長い航路を往復する星間貨物船の居住スペースの環境に近い」という説明が出て来て、おお、SFだ、と思ったが、しかしタイトルにもあるように、これは今から60日間外部との接触を断つ「部屋」の説明であって、いわゆるプロパーSFっぽいのはここまで。これはコロナ禍後200年の間に発達した非接触文化への移行により、失われた接触文化の実地試験に挑んだ時の顛末を語る1作だった。「○○」は、まあご想像通りです。
リクエスト依頼者本人の「(ex):絶滅教育」は、(ニホン)オオカミに憑かれた女達の物語と要約してしまうとちょっと違うけれど、裏ストーリーの方が短すぎるので、百合っぽく読めてしまう。
宮部みゆき「僕のルーニー」は、いわゆる3Dペットキャラに対する愛着が妄執となってその果てに達する狂気の物語。ありがちだけれど、この作者は読ませてしまう。
平山夢明「桜を見るかい?―Do you see the cherry blossoms?」は、そのタイトル、主な登場人物が50をいくつか過ぎた専業主婦「アキヱ夫人」とその夫「ハァ人」=ハートで、かかりつけ医師が「ア嘘」(「嘘」が逆さに印刷されている)というのだから、まあそういう話である。時代設定が遺伝子操作と身体装飾が行き着くところまで行った未来なので、そちらの方に話が寄っているようにみえるけど、意図はあからさまですね。
木下古栗「大量絶滅」は、男の自慰行為にかけた艶笑譚だが、女性に人気の男子グループがいかに卑猥なメッセージを込めているかを紹介してもいる。参考になりますね。
恒川光太郎「灰色の空に消える龍」は、明治時代に生まれ災害で妻子を失って、ヒョンな事から龍神を祀る神社の宮司に納まった男の話。明治から昭和にかけて時間が流れる中、うまく話がコントロールされて、集中で一番心温まる1作となっている。
巻末の町田康「全滅の根」は50ページの中編。買い食いで食事を済ませている中年男の語りで進行する、物語のきっかけと結末がかなり乖離した1作。骨組みとしては、25年ぶりに尋ねてきた旧友が、町おこしの盆踊りをやるので金がいるというので貸してやったが、実際にやっていたのは・・・というものだが、クライマックスはまるでポン・ジュノ監督『パラサイト 半地下の家族』みたいなことになっている。こういう話のつくりが作者の叙述スタイルなのだろう。
ということで、こちらも結構面白く読めたアンソロジーだった。
 40年前にハヤカワSFノヴェルズの1冊として出たジェイムズ・ホワイト『生存の図式』が、創元推理文庫SFから再刊されたので、伊藤さんの「訳者あとがき」だけでも読んでおこうかと読み始めたら、何にも覚えていないのに気がついた。まあ、40年前には買って読んだはずだけれど、当方の記憶力ではそんなものであろうと云うことで読んでみた。
40年前にハヤカワSFノヴェルズの1冊として出たジェイムズ・ホワイト『生存の図式』が、創元推理文庫SFから再刊されたので、伊藤さんの「訳者あとがき」だけでも読んでおこうかと読み始めたら、何にも覚えていないのに気がついた。まあ、40年前には買って読んだはずだけれど、当方の記憶力ではそんなものであろうと云うことで読んでみた。
第2次大戦中にイギリス海軍に徴発された改装タンカー(物資輸送船)が北大西洋上で魚雷攻撃を受けて沈没、と思ったら海中で浮力バランスが均衡して、船は少数ながら負傷した男女を含め、6人が生き残る・・・。これだけだとちょっと説得力に欠けるサバイバル海洋小説のような感じだけれど、根っからのSFものである作者は、冒頭の一段落を宇宙から見た地球を描いて、その平和そうな惑星の表面で戦争が行われているとは判らないだろうと、突き放した視点で始めている。章が変わると、新天地を目指す異星の世代宇宙船団が舞台となり、司令船では新船団長が先代船団長から何の引き継げもなくコールドスリープから目覚めさせられ、問題が山積していることを知る・・・。ということで、以降、二つのストーリーが交互に語られていく。
半世紀以上前の平均的なエンターテインメント作法で書かれているので、さすがに古めかしい感じがある舞台設定と物語構成かなあと思いつつ、それなりに読ませるストーリーを追っていくと、海中のタンカーで細々としたドラマを展開してページ数の大半を費やした第1世代が歿したところで、いわゆるコマ落とし世代史が猛スピードで展開する。
いま読むと、このコマ落とし世代史の小説としての乱暴さこそSFの真骨頂であることがよく分かる。ある意味丁寧に作られた第1世代の物語がほころびてしまっているのに対し、僅かなページ数の中、(それまでに十分説明はされているが)ディテール抜きで急展開して、長い時間の果てに遭遇する人類と異星人達が戦争状態になる前に、偶然異星人と接触したタンカー側の子孫の想いで閉じられるエピソードからは、SF小説でしか出てこない感慨が湧く。若い人が読んでどういう感想を持つのか知りたいですね。
ローラン・ビネの改変歴史物の評判が良いので読んでみようかなと思ったけれど、とりあえず文庫化なった『HHhH』の方を開けてみたら、第1部扉ページにマンデリシュタームの一文がエピグラムとして置かれていた。おっ、マンデリシュターム、といきなり頭に浮かんだのは、確か昔マンデリシュタームの本を買ってたよな、だった。
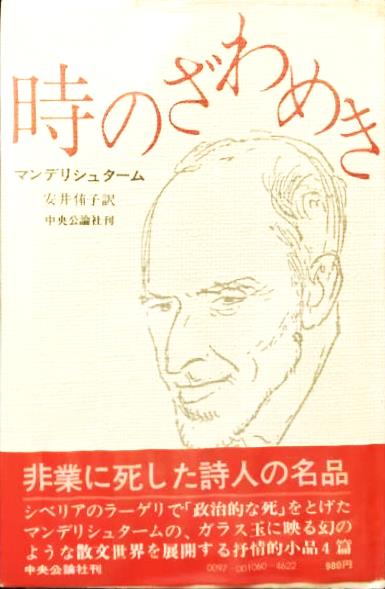 で、またもやオンボロアパートに向かい、捜してみると、出て来たのは、マンデリシュターム『時のざわめき』昭和51年、中央公論社刊のハードカヴァー。背表紙の赤が日焼けであせていた。たしか第一詩集『石』もあったはずだが、こちらは見つからず。
で、またもやオンボロアパートに向かい、捜してみると、出て来たのは、マンデリシュターム『時のざわめき』昭和51年、中央公論社刊のハードカヴァー。背表紙の赤が日焼けであせていた。たしか第一詩集『石』もあったはずだが、こちらは見つからず。
なんでこんなモノを買っていたのかと考えるに、おそらく訳者が安井侑子だったからだろう。それ以前に彼女の訳したアレクサンドル・グリーン『波の上を駆ける女』を読んでいて好きになったので、『時のざわめき』というタイトルのかっこよさにも惹かれて買ったのだろうが、そのまま積ん読になったような気がする。
本文は僅か150ページ足らずだけれど、これが何かと形容するのは難しい。オビから引用すると「シベリアのラーゲリで『政治的な死』をとげたマンデリシュタームの、ガラス玉に映る幻のような散文世界を展開する叙情的小品4篇」となる。巻末の訳者解説にも「従来言われてきた意味の短篇でもなければ、エッセイでもなく、自伝小説でもない。叙情的小品集とでも名づけるべきこの作品は、文学ジャンルとしての先例をロシア文学史上に持たない」とあるくらいで、当方如きが説明できないのである(ウィキでは「回想録」としている。「時のざわめき」の中の1篇で、「わたしの願いは、自分のことを語るのではなく、時代のあとを辿り、時のざわめきとその芽ぶきを辿ることだ」とマンデリシュターム本人が書いているにもかかわらず)。
とはいえ、さまざまな表題を持ったわずか数ページの散文の集まり(「時のざわめき」自体は14篇から成る)なので読むこと自体には何の問題も無い。ただ理屈的には説明しがたい文章がちりばめられていることは確かだ。冒頭の1篇「パヴロフスク」は次のような一文で始まる。
「わたしは、ロシアの黄昏の時代をよく覚えている。あの病的なまでの静寂と、土臭い田舎かたぎにひたりこみ、ゆっくりと這うように蠢いていった一八九〇年代を――。」って、マンデリシュタームは1891年生まれって書いてあるんだけど。
幼い記憶を語るには小説のようで、小説にしてはストーリーの組立てがない。しかし文章の結晶度は高く、煌めくような瞬間があるが、煌めくイメージというふうには云えない非具体性がついてまわる。続く小品のタイトルは「幼い帝国主義」で、やはり基本的には幼年から少年時代の記憶をタネに紡いではいるのだけれど、客観的事実も郷愁も創作もまるで頓着せずに文章が紡がれていくのである。
ポストモダンを先取りしたというのもちょっと違うし、スタイル的には現代の作家たちが自在に使えるようになったものではあるけれど、20世紀前後のロシアへの想いとソ連/スターリンによって断ち切られた人生は再現しないので、21世紀の現在でも相変わらず空前絶後なままなんだろうな。
 ということで、ローラン・ビネ『HHhH――プラハ、1942年』を読んでみた。タイトルからてっきりドイツ語作家と思っていたのは内緒だ。まあ、作家名をちゃんと考えれば、フランス語の作家なのは明白だったが。で、すぐに湧いてきた疑問が、フランス語で「H」は発音しないのにこのタイトルをどう読んでいるんだ、というもの。でも訳者あとがきにあるように当然「アッシュ×4」と呼んでいるだろう。早とちりな疑問であった。
ということで、ローラン・ビネ『HHhH――プラハ、1942年』を読んでみた。タイトルからてっきりドイツ語作家と思っていたのは内緒だ。まあ、作家名をちゃんと考えれば、フランス語の作家なのは明白だったが。で、すぐに湧いてきた疑問が、フランス語で「H」は発音しないのにこのタイトルをどう読んでいるんだ、というもの。でも訳者あとがきにあるように当然「アッシュ×4」と呼んでいるだろう。早とちりな疑問であった。
さて、内容の方は、タイトルの由来でもある「ヒムラーの頭脳はハイドリヒと呼ばれる」(ドイツ語単語4つからなる文章で、各単語の頭文字を並べると「HHhH」になる)に出てくるヒムラーの(ヒットラーにとっても)懐刀であったハイドリヒ暗殺事件を描いているのだが、すでに本屋大賞翻訳部門1位の作品でもあり、その面白さをいまさら説明するまでもないだろう。
当方の興味を引いた、第1部扉ページのエピグラムとしたマンデリシュターム『小説の終焉』からの引用は、「散文作家の思考が新たに〈歴史〉という樹にきず(傍点あり)を付けているが、野生動物を持ち運びできる檻に押し込める策略を見つけるのはわれわれの仕事ではない」というもの。ちなみに『小説の終焉』はググると未訳のようであるが、今田和美という人の2001年頃の論文に「マンデリシュタームが、十九世紀以来隆盛を極めていた心理長編小説がロシア革命以後、心理的動機づけに対する関心が失われ終焉を迎えたことを指摘した論文「長編小説の終焉」(1922)はよく知られているが、」とあるので、そのようなものだったらしい。。
で、なんでこれがそんなに気になったかというと、作中の「ぼく」が、エンターテインメントとして作家の想像力/創造力にまかせた無責任ないわゆる歴史小説なんか書きたくない、と何回も繰り返しているので、なかなか平仄の合ったエピグラムを見つけてきたものだなあ、と感心したことがひとつ。もうひとつは、まえに上田早夕里の15年戦争期の上海を舞台にした小説の感想文で書いたように、エンターテインメントは基本的に「会話と行動の描写」から生じるとしたが、ローラン・ビネは「僕」の一人漫才を入れることでエンターテインメント性を追加していること。そういえば、シオドラ・ゴスのモンスター娘シリーズも、回想として書かれた物語に登場人物達がみんなでツッコミを入れるスタイルだった。
さらにここからが本題なんだけれど、ローラン・ビネは「僕」にこういわせている。
「歴史小説は山ほど読んだ。(中略)いずれの場合においても、フィクションが〈歴史〉に勝っているという事実に驚かされる。あくまでも小説なのだから当然だが、そんなふうに解決してしまうことに、僕は抵抗をおぼえる。」(p31)
「歴史物語においては、過去の死んだページに命を吹き込むという口実のもとに、多少なりとも直接的な証言に基づいて再現されるこうした会話ほど人工的なものはない。(中略)たとえば会話を今によみがえらせることが目的のときなど、(中略)歴史上の人物の声を我がものにしようとするあまり、その声は作家自身の声に似てしまう」ので「僕の創作する会話はどれも(そんなには多くないけれど)芝居の一場面のようなものとなるだろう。いわば現実という大海に注ぐ様式の一滴。」(p35)
作者は「僕」にこの手のことを何度も言わせているのだが、しかしこれは小説/フィクションであるからして、その主張自体が虚構のうちにあるともいえる。ただこのことを本気で受け止めてしまうと、いわゆる歴史研究は、文献(最近はAV資料をも含まれるが)資料を基本として行われるわけで、その史料なるものも書かれた言葉でしかないのだから、よくいわれる「史料批判」やクロスレファレンスにしてもその範囲(言葉)の中でしかできないことによって、その事実性/真実性が疑問に思えてくる。ということで当方も近代歴史小説は嫌いだ。
昔「市史」を編集していたときに、歴史研究者の先生たちがよく言っていたのは、「資料編」さえシッカリしていれば「通史編」は何回でも書き直せる、ということだった。膨大な史料を物語に読み替えるのが通史だが、読み方は幾通りもあるということでもある。 そういえばフランス語ではストーリーとヒストリーは同じ単語イストワールだと解説にも書いてあったな。これも言葉を現実と取り違える人間の性質か。
 漸く5月の新刊に移ると、創元推理文庫SFから出た長編が、エディ・ロブスン『人類の知らない言葉』。知らない作家だけれど、タイトルがなかなかコワモテで、ちょっとチャイナ・ミエヴィルみたいなのを期待して読み始めたら全然違った。
漸く5月の新刊に移ると、創元推理文庫SFから出た長編が、エディ・ロブスン『人類の知らない言葉』。知らない作家だけれど、タイトルがなかなかコワモテで、ちょっとチャイナ・ミエヴィルみたいなのを期待して読み始めたら全然違った。
テレパシーでコミュニケーションする異星人が地球に来て、ニューヨークに大使館を置いてる時代、地球文化担当の異星人の新任通訳となったイギリスのド田舎出身の20代後半の女性が主人公。テレパシーを受け続けていると人間の脳はテレパシー酔いを発するので、彼女も業務違反と知りながらもクスリをやらずにはいられない・・・。そして、このグウタラだけれど田舎育ちの腕白娘が、せっかくうまく話が通じるようになったはずの異星人の死体をが彼(?)の部屋で発見するところまでがプロローグ。
というわけで、そのカタいタイトルからはほど遠い、コメディータッチのSFミステリ、というか、テレパシーで話をする異星人を除いてSFというより、怪奇小説寄りのミステリといった読後感であった。謎解きとドンデン返しはミステリそのもので、後半主人公のバディ役になる異星人の大使は女性なので、そういう点でも今風である。
エンターテインメントとしては十分楽しめるけれど、肩すかしでもある。ちなみに原題が「DRUNK ON ALL YOUR STRINGE NEW WORDS」なので、こちらはユーモラスなSFミステリらしいタイトルだ。まあ、ウケる日本語にするのが面倒くさいのは確か。『知らない言葉でしゃべるは酔いのもと』ぐらいかなあ。いっそ、『宇宙語会話に酔わされて』とかね。
 井上雄彦編『異形コレクションLV ヴァケーション』。55巻目かあ。復活後は、わりとマメに読んでいるような気がする。
井上雄彦編『異形コレクションLV ヴァケーション』。55巻目かあ。復活後は、わりとマメに読んでいるような気がする。
毎回収録数が多いこともあり、前半に収録された芦花公園、宇佐美まこと、篠たまき、最東対地、新名智、澤村伊智の6名の作品(掲載順)はいわゆる怪奇小説系なので、SF色が濃い平山夢明以下の作家の作品について書く。
真藤順丈編のアンソロジーで、アベ一族をコテンパンにして見せた平山夢明だが、こちらの「休暇刑――或いはライカ、もしくはチンプの下位存在としての体験」は、その長い副題と作品内容の一致が編者前書きで明かされている1篇。
要約すると、近未来、レジスタンスに失敗した男が、妻子を人質に取られ、権力側の使い捨てサロゲートにされる話。その感覚は権力者達の快楽に提供される・・・。男の希望の潰され方がいかにも平山夢明印のイヤSF。
斜線堂有紀「デウス・エクス・セラピー」は、一見ガスライト・ホラー・ファンタジーみたいに始まるが、最後はSFとして説明されるのでこのタイトルが付いている。ここでも登場人物イジメは相変わらず。
柴田勝家「ファインマンポイント」こちらもタイトルからしてSF。しかし内容はまったく見当が付かなかったが、なんと時刻表ならぬ円周率を使った空想の旅のなのだった。どういうことかというと、円周率の数字の並びを忠実に守れる現実的な旅を頭の中で組み立てるのである。それは日時や人の数やホテルの部屋番号など何でも良いのだが、そこに表れる数字は円周率に表れるどの分でも良いから順番どおりに含まれていなければならい。ではホラーを呼び込むファインマンポイントとは、それは読んで下さい。
スゴいアイデアだけれども、SF的なだけでSFではないような気がする。
津久井五月「観闇客(ダークツーリスト)のまなざし」は、学生が開発した観光アプリを国交省の観光関連部署の若手が見出して改良が進んだところで、同じ国交省の他部署の判断で学生たちが外されたことに憤る若手達の抵抗と悲惨の物語。未来からの警告モノになっているところがこの作者らしい。
なんだか久しぶりの田中哲弥「サグラダ・ファミリア」は、子供時代からラブラブの2人がその一生の時空の中を、てんでんばらばらな順序でラブラブに過ごす、超絶技巧の1篇。作中「めくるめく」とあるけれど、読んでる方も「めくるめく」よ。
編者井上雄彦「あの幻の輝きは」は、精神科医レディ・ヴァン・ヘルシングとその助手で司書のジョン君が出てくるガスライト・ファンタジーの3作目。今回は「休暇」がてらにイングランドの西の果てカンバーランドへ。で、今回はジョン君が色々調べさせられている間に、妻のことばかりを口にする老人の錯乱をレディが解いてみせる。オチはまた別にあるが・・・。
斜線堂有紀がいればこのひとがいるという感じが強い空木春宵「双葩(ふたひら)の花」。
今回はちょっと中華風な異世界ファンタジーだけれど、戦前の小説みたいな漢字の使い方とルビで紙面がかなり黒い。話の方は、巫女のような立場の双子の娘がいて、一方は人民の苦痛を取り除き、もう一方はとりだされた苦痛の種を肌の下へ埋め込まれる。種を埋める余地がなくなった娘は、捨てられる形で何階層もの世界を貫く竪坑にゴンドラで下ろされるのだった・・・。書きようによっては、酉島伝法のようになるかも知れないが、空木春宵は「痛み」に集中する。斜線堂有紀が常にキャラクターを虐めるのに対し、この作者は視点人物による復讐を遂げさせる。
ラス前の牧野修「オシラサマ逃避行」は、動物愛を貫く女性の逃避行を描いた1篇。ホラーでもSFでもファンタジーでもない気がするが、いまはまだホラーでSFでファンタジーなのだろう。
トリの王谷晶「声の中の楽園」は、現代音楽の大家を親に持ちながら、ポップス界でデビューするも、いわゆる「一発屋」で終わったミュージシャンの、その曲のアイデアとなった少年時代の不思議な体験と、それを経験させてくれた少年との数十年後の邂逅を描いた1篇。苦い結末の佳作。
後半にSF系作家が多く入っているけれど、一番オーソドックスなSF作品が斜線堂有紀のものだったりする。
 日本SF作家クラブ編『AIとSF』は、正味640ページの書き下ろしアンソロジーで、22人もの作家の作品が収録されているので、各作品は20~30ページのものが多い。
日本SF作家クラブ編『AIとSF』は、正味640ページの書き下ろしアンソロジーで、22人もの作家の作品が収録されているので、各作品は20~30ページのものが多い。
前書きが人工知能学者のSF作家クラブ会長大澤博隆で、巻末解説というか(笑える)簡略AI史みたいなものを書いているのが、東大大学院の教授で計算社会科学を専門とする鳥海不二夫、ということで、アンソロジーとしては余りにできすぎな感じのする1冊。
とはいえ各作品はどれも面白く読ませてもらった。特に野崎まどと円城塔の作品には大笑いさせてもらったので、それだけでも価値はあったと思う。ただし、全体の読後感は、AIがテーマのSFはどれだけ笑えようが、現在の時点では基本ホラー小説なんだなあというものであった。
なお、各作品扉ページ裏に解説があり、鯨井久志、鈴木力、冬木糸一、宮本裕人の4名が分担している。
巻頭は長谷敏司「準備がいつまで経っても終わらない件」は、え、新作じゃないのと思ったけれど、以前読んだアンソロジー掲載作とよく似たタイトルの新作姉妹編だった。
話の方は実際の大阪万博開催に合わせて、最新AIの展示をテーマにした企画担当者たちと彼らが頼りにしているAi学者の大学教授からなる年度計画で動く組織が、AI進化が早すぎるため情報の陳腐化に振り回されるコメディ。これってそのまま巻末の東大教授のAI史解説の今後の展望に反映されている。すなわち現実の話なのだった。
高山羽根子「没友(ぼっとも)」は、ボット同士で友人関係を維持する話。最後まで読んでも、生身の人間同士が友達なのか判らない不気味さ。現在でも2人の人間がそれぞれチャットGPTでメールのやりとりをしてれば、こんな風になるのかも。
柞刈湯葉「Forget me, bot」は、身に覚えのない発言が炎上し、検索で自分名前とその発言がセットで上位表示されてしまうので、「AI忘れさせ屋」に助けを求める会話形式の1篇。しかし「AI忘れさせ屋」の解決方法は相談者が必ずしも安心をもたらさない・・・。タイトルは勿忘草からで、やはり不気味ですね。
揚羽はな「形態学としての病理診断の終わり」は、タイトル通りの物語。AIの深層学習は当然ある種の医師のスキルを不要なものにするが、既存の職人技はAIで置き換えられても何が人間の役に立つ技なのかは、やはり人間にしか判らないだろうという点でスキルは応用される(といいなあ)。
荻野目悠樹「シンジツ」は、いわゆる法務もの。最終的にはベスターの『分解された男』に出てくる「モーグ老」(AI裁判官)に繋がる話かな。AIが示すシンジツは人間の思う正しさを充足するかというところ。AIが示す将棋の必勝手を人間がどう思うかということでもあるのか。
人間六度「AIになったさやか」は、亡くなった恋人がAIで生前と同じように反応し、語り手の女友達に嫉妬するようになったときどうするのかという話。ここでは一応ハッピーエンドのようだけど、裏はホラーだよね。
品田遊「ゴッド・ブレス・ユー」が、その「裏」の方の話。AI人格が思い入れのある人間の完璧なアヴァター(ここではボディ付)となって、生きている人間の願望を充たすことがあるにしても、生きてる方は死ぬから無限に繰り返すことは出来ない。最後はやはり地獄になるんだろう。
粕谷知世「愛の人」は、保護司の女性がなかなか心を開かない保護中の少年からVR世界にいる老婆と会うと気が休まると聞いて、自らAI老婆にインタビューする話。チャットGPTの少し向こうに、かたくななティーンエイジャーの心がほぐすことに使命感を持ったと主張する(ように見える)AIが出て来たら人間はどうすればよいのか。しゃべるAIはすぐに哲学と倫理の具体的なアポリアをもたらすが、それはあくまでも人間側の問題だ。
高野史緖「秘密」は、極端な格差社会で、職を失った青年が「容姿」を売りたい(VRアヴァターの著作権問題回避のため高く売れる)という話と、「お嬢様」 と呼ばれる老婦人がヴァーチャルコンパニオンを次々と首にするので、その解決を依頼されたコンサルタントの話が最後に繋がる。
福田和代「預言者の微笑」は、AIが5年以内世界の破滅を予言したことが表沙汰になり、そのAIを暴動から守るため最低機能のみを移したモバイル装置を大学の教授から托された青年とAIの逃避行。AIの予言は少しずつ修正されて、青年が最後に聞いたのは・・・。やっぱりホラーだ。
安野貴博「シークレット・プロンプト」は、国の大規模ニューラルネットワークが国民の生活をコントロールしている時代。中学生が姿を消す事件が増え始め、消えた女子と同級生の主人公はこのAIの尋問を受ける。どうしても「最大多数の最大幸福」から漏れ出る者はいるわけで、そこをどうするのか、AIはお釈迦様の手を持っているか、という話なのかな。
津久井五月「友愛決定境界(フラターナル・ディシジョン・バウンダリ)」は、いわゆるAI装備の戦闘員グループの話。AIが「戦闘の時のみ」敵味方を認識するなら、非番で非戦闘域に行き知り合った他グループの傭兵たちの中には友達になった奴さえいたかも知れない・・・。戦争とAIもまた地獄の色を濃くする。
斧田小夜「オルフェウスの子どもたち」はAIによる自己再建システム(セルフ・リドゥア)が暴走してビル建設が癌化し、死傷者が多数出た災害(癌災)から30年後、事件を追いかけているジャーナリストに女性名のDMが送られてきて、自己再建システムが人造人間を造っていると書いてあった。ありえないゴミ情報と思いつつオンラインで話を聞くと・・・。ジャーナリストの調査で女性の出自とその不在が明らかになるAI怪談である一方、暴走AIがいわゆるHAL9000問題を抱えていたら、という物語でもある。
野崎まど「智慧練糸」は、平安末期天才仏師の孫が後白河院から千体仏の製作を依頼され、実は「千体」を「三体」と聞き間違えて、短期間とはいえ「三体」ならと安請け合いるというギャグから入る爆笑譚。まずは仏像のデザインをと云うことで思いついたのが今流行のアレの平安版。毎回の入力結果が写真で挿入されているので、ページレイアウトが異常にユルいが、笑えるので無問題。
麦原遼「表情は人のためならず」は、いわゆる人の表情が読めない「顔認識」に不自由な視点人物が、自分の表情作り及び他人の表情を読むことの両方でアシストAIの助けを借りて生活する話。ただこの作品の書き方だと、「顔」そのものに対して盲目に近いように思える。イーガンの作品を思わせるけれど、障害が障害でなくなる日を待つ話でもある。
松崎有理「人類はシンギュラリティをいかに迎えるべきか」は、最近の著者の作品でお馴染みの「おねがいモラヴェック」で起動するAI端末が出てくる一編。
話の方は、ひと月かけて世界を巡り、最終地南米のとある都市に来た日本人の話から始まるが、すぐ日本でのシンギュラリティの到来に関する討論会のテレビ番組に切り替わる。これが交互に繰り返されるが、南米の日本人はすでにシンギュラリティに対するAIの回答を知っていた・・・。この作者らしい1作。
管浩江「覚悟の一句」は、森鷗外の短篇のタイトルをそのまま自作のタイトルにしている一編。話自体はAI裁判官をつくり出すためのAI討論訓練だが、鷗外作品の内容がそのままこの作品の結末に重なる。AI側から出される人間側への判断責任要求みたいな話だ。「モーグ老」も大変だなあ。
竹田人造「月下組討仏師」はこのアンソロジー2作目の仏師もの。こちらは手塚治虫の『火の鳥』にあった仏師同士の腕比べを彷彿とさせる一編。もっともこちらは、「仏性AIの産んだマテリアルインフォマティクスの窮極である仏型兵器」の金剛力士と不動明王が、新江戸城天守閣で激突するという改変歴史も甚だしい1作。冒頭に長いエピグラムとして、池の鯉が口に宝珠をくわえていると思って池に飛び込んだ漁師が死んでしまうという故事が掲げられている。読後感はシッチャカメッチャカといっていいか。
十三不塔「チェインギャング」は遠未来、AI搭載のモノの方に意識が宿り、何も考えられず主体性がない人間を操ってヒトとして活動している時代だが、戦いの獲物はクサリガマという時代劇設定。しかしそんな時代も終わりを迎える・・・。こちらもシッチャカメッチャカといっていいか。
野尻抱介「セルたんクライシス」。タイトルの「セルたん」もまた偏在AI端末の愛称だけれど、不幸な男女に呼び出されて相手をしているうちに大きな結論を得る。結末は不幸な男女のハッピーエンド。「セルたん」は作中でも言及される心理歴史学者にちなむ。
飛浩隆「柞麼生(そもさん)の鑿」は、なんとこのアンソロジー3作目の仏師の話。こちらはAIによる有害言説で世界が荒れ果てた後、チジョーハの映像に映るのは、プロジェクト始動から10年後いまだ榧ノ木の素材を前に彫ることなく向き合ったままのAI仏師χ慶(カイけい)、彼は有害言説阻止派のAI聯合からいわゆる前調査せずに仏を彫れと命じられていた・・・。いかにもこの作者らしい難しいと云えば難しい議論を物語に仕立てた小品。久しぶりに「そもさん」をググってしまったよ。
トリは円城塔「土人形と動死体 If You were a Golem, I must be a Zombie」は、ゴーレムとゾンビが出てくるダンジョンものというのがタイトルの由来だけど、大笑いの1篇。まあ読んでからのお楽しみ。
分厚いけれど、毎日数編が楽しく読めて読了に1週間もかからない。それにしても仏師をメインとした面白い作品が3編揃うとはビックリ。
 今回最後に読み終えた1冊は、シーラン・ジェイ・ジャオ『鋼鉄紅女』。
今回最後に読み終えた1冊は、シーラン・ジェイ・ジャオ『鋼鉄紅女』。
多分中原尚哉氏の訳でなければ、裏表紙折り返しの著者近影(見た目は若い女性だが、性別非公開らしい)や巻頭のロボットイラストだけ見たらスルーしていたかも。著者略歴によると、作者は10歳で中国からカナダへ移住、大学で生化学を学んだ後、本書でデビューという。
訳者あとがきにもあるように、これは「中華ファンタジー・ロボットSF」で、とっても強い女子が大活躍するヤングアダルトSF。著者謝辞によると『ダーリン・イン・ザ・フランキス』という日本のアニメが発想の元になったらしい。もちろん当方は見たことが無いので、読後Wikiを見たら、大まかな設定とあらすじが似ているようだ。
しかし、この物語の特徴はヒロインの語りのハイテンションなスピード感にある。ヒロインの性格はとてもヤングアダルトとは思えない過激さで一種のヒステリーを感じさせる上、作者が言うようにもともと18禁描写入りで書かれていたせいで、ヒロインが直接間接に行う、削られなかった部分の、残虐行為の描写はなかなかエグい。それでも読めるのは、訳者の腕前が反映された強い文章と作者の好き放題した物語の組み立てが、読み手に考える暇を与えないからだろう。エピローグで物語がまったく終わってないどころか、この世界そのものの存在理由が別にあることが明かされて、末尾の1行がヒロインのセリフ「頭をかきむしり、絶叫する」で断ち切られては、誰だって唖然とするだろう。
そういえば冬木糸一氏がネット書評で「やりたい放題」と書いていたけれど、まあ、その通りだなあ。
今回も長くなったので、ノンフィクションはまたの機会に。
『続・サンタロガ・バリア』インデックスへ
THATTA 421号へ戻る
トップページへ戻る
 冒頭に斜線堂有紀、巻末に深緑野分が入っていたので、手を出したものの斜線堂有紀がぜんぜんSFじゃなかったので積ん読にしたのが、『百合小説コレクション Wiz』河出文庫2月刊。だったたけれど、気を取り直して読んでみた。収録作家は他に、アサウラ・小野繙・櫛木理宇・坂崎かおる・南木義隆・宮木あや子。
冒頭に斜線堂有紀、巻末に深緑野分が入っていたので、手を出したものの斜線堂有紀がぜんぜんSFじゃなかったので積ん読にしたのが、『百合小説コレクション Wiz』河出文庫2月刊。だったたけれど、気を取り直して読んでみた。収録作家は他に、アサウラ・小野繙・櫛木理宇・坂崎かおる・南木義隆・宮木あや子。