

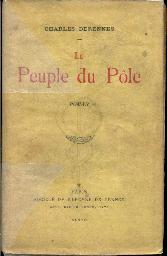
パリへのバイオテロつながりの次は、フェミナ賞つながり。1925年のデルテイユ受賞の前年1924年、Le Bestiaire sentimentalで、フェミナ賞をとったのがシャルル・ドレエヌ(Charles Derennes、1882〜1930)。カナ表記はドゥレンヌ? ドゥレエヌ? と悩んだが、シンプルさを買って『新興仏蘭西文学』白水社、1931年での表記を採用。同書で「この作家には詩才が溢れてゐるのである…彼の詩には、ガスコン風な屈託のない気分と何物をも悲劇的に見ることを拒む朗かな明るい心のもつ伸びのびした気質とが深く泌みこんでゐるやうに思はれる」とされるドレエヌは、主に南西フランス地方色を前面に出した作品で評価された作家だったようだが、若気の至りで処女作に続く第二作として書いちゃったのは野心的なサイエンティフィック・ロマンス Le peuple du pole(1907)だったのである。
で、これを翻案(抄訳)したのが押川春浪の『北極飛行船』本郷書院、1909(明治42)年。この連載のパターンとしてがんがんネタは割られるものと覚悟していただきたく、そんなわけで未読の人はまず国立国会図書館の近代デジタルライブラリーへGO。
読んできましたか。
どなたなのか存じ上げないので、ここでお名前をあげることができず大変申し訳ないところだが、その昔『世界文学にみる架空地名大事典』講談社、1984年(その後『完訳世界文学にみる架空地名大事典』2002年が出た)を読破した人が「北極王国」の項目を見て「極地の民」って春浪じゃね? と気づかれたのだそうである。いや、偉い人がいるものである。
まず、引用
「●北極王国●North Pole Kingdom 北極圏の地下にある国。文明を持つ恐竜が住む。迷路のように入り組んだ地下のトンネルと、氷原に通じる七つの出入り口からなる。恐竜の社会は細心の配慮の下に組織され、そのすべての構成員が専門職を持つ。中心となる仕事は、北極の電磁エネルギーを熱と光に変換する巨大な機械を監視することである。この仕事に責を負う労働者には、必ず若年の弟子が付き添うことになっている。万一、労働者が自らの責務を怠った場合に、弟子が即座に仕事を引き継ぎ、労働者は死刑執行所へ送られるようになっているのである。恐竜の衣服は、アザラシの毛皮で作られたオーヴァーオール様のものである。顔は大トカゲの顔に似ており、何の感情も表わさない。…略…(シャルル・ドゥランス、『極地の民』、パリ、一九〇七年)」
ドゥランスという表記は、どうかということでドレエヌにしちゃいましたが、それはそれで違うというご意見もあるやろね。いや、促音が無い方が書きやすかろうと思ただけなんやが。しかし「ス」ってヘンやねえ、やっぱり「ヌ」の誤植なのをつっぱねとるのか。完訳版でも変わっとらんのよな。追加された「アグツュアジギュル」の項目では「ヌ」と書いてあるけど、索引と北極王国の項目は前の「ス」のまま。下訳を担当した学生が出世してしまったので、恐れ多くていじれない…ということはないと思うので、単なる見落としでしょうか。Nの項目を担当していた人は、明治大学先生になられたんですか、そうですか。
このLe peuple du poleは英訳された形跡がないため『北極飛行船』はフランス語からの翻案ということになる訳だが、春浪がフランス語を学んでいた事実が確認されていないため、本作も春浪にありがちな名義貸しではないかと見られている。
では、本来の翻案者は誰だということになるし、さらには、春浪作品の多くにフランスがからんでくるあたりに、誰かブレーン役がいたという可能性を考えなくてよいのかという疑問もわいてくる。
そのあたり、会津信吾+横田順彌に続く春浪研究の待たれるところである(いや、もちろん第一人者お二人のさらなる研究にも期待してますけど)。
この作品は、もっと早くに取り上げるつもりでおったんやが、去年、下調べしたら来年英訳が出る予定やとかいうんで、一年埋めとったのである。いや、そのまま埋もれて出てこなくならなくて良かった良かった。
英訳したのはブライアン・ステイブルフォード。知らぬ間に、ブラックコートプレスと組んでフランスの古典的SFをガンガン出してますよ。
ちなみに、Le peuple du poleは2007年時点でネットで探しても売ってないレア本とか解題で書いとるが、ブライアンすまん、なんや売っとるやん、と俺が買ってしまったよ。
ということで、探し方が悪かったか、2007年のある特定の時期には売ってなかったというのが正確だぜ、ブライアン(友達かよっ)。
あと、1995年にスペイン訳があるっきりで、ドレエヌの生前には再刊もされず、2002年にマニア向けに250部リプリントされただけ、とか書いてるけどスペイン語訳は1921年にマドリッドのJimenez y MolinaからManuel Abril訳があって、1994年にAnayaからJavier Martin Lalandaによる新訳が出た、ってのが正確なところでは。ブライアンのお友達で見ている人がいたら、日本で同時代に訳されているってことと併せて教えてあげていただきたい。

いや、翻案ぶりが微妙なので、どっかに埋もれた英語でのアダプテーションが当時あって、それをベースにして『北極飛行船』が出来たのではないかという疑問も。
とりあえず押川版と対応させた章題を以下に示す。
PROLOGUE/奇異の発端/DEUX HOMMES, DEUX CHIMERES/[省略]/LES CAVALIERS.../[省略]/...ET LEUR MONTURE/[省略]/PROPOS ENTRE CIEL ET TERRE/飛行船の出発 未知の世界/LE JOUR VIOLET/神秘の関門/SUR LA PIERRE BRUNE/飛行船の墜落/CEINTRAS EGARE SON OMBRE ET SA RAISON/城砦の様な巨巌 怪しき扉/LA FACE AUREOLEE D'ETOILES/失望の一夜/HEURES D'ATTENTE/苦心の結果/L'ETRE SE MONTRE/北極人の出現 最後の手段/EXCURSIONS SOUTERRAINES/悲しき運命/FAUX DEPART/憎むべき仮面/L'AGONIE DE LA LUMIERE/洞窟内の大格闘/ECRIT SOUS LA DICTEE DE LA MORT/ああ絶望/EPILOGUE/[省略]
『北極飛行船』はプロローグを「奇異の発端」として短く紹介した後、原書第一〜三章の探検計画のスタートや飛行船開発の苦労の部分はばっさり落として、飛行船がいよいよ北極を目指して飛行を開始するところからはじまる。
原書のプロローグでは話者とLouis Valentonが実際に対話しているのだが、押川版は、ロウイス・ファレントンからの手紙によって経緯が語られ、次章以降にファレントンが入手した北極探検の記録を話者が書き起こすことになっている。押川版はプロローグで、これをウオルタア・ウヱルソンの北極への飛行船による探検の記録だとし、実際にあったWalter Wellmanの探検計画(原書でも言及される)を物語にまぜこんでいるのだが、物語は「T、Hと云ふ、哀れなる探検家の記録は此所で終つてゐるのである。」で終わっていて、辻褄があってません。
大体、T・Hって誰なんだよ。原書では、探検の記録は飛行船建造の資金を出したJean-Louis de Venasqueによって記されたもので、その相棒が飛行船を建造した技術者Jacques Ceintras(押川版では高木)で、北極に赴くのはこの二人だけなんですが。
じゃ、翻案じゃないのではと思われるかもしれないが、例えば飛行船での食事シーンをご覧いただこう。
押川版
…然し、高木の先生、私の此の『愉快』には少々物足らぬと云つて、『兎の佃煮も十分暖つてゐなし、葡萄酒も余り冷た過ぎるし、ビスケツトと随分ゴツゴツしてゐるから、事によつたら、僕の胃袋を破るかも知れん。』
ステイブルフォード訳
Ceintras, of course, did not share my opinion. The jugged hare was not warm enough; the Bordeaux should not be drunk so cold; the biscuits would certainly give him a stomach-ache...
原書
Bien entendu Ceintras ne fut pas de mon avis: le civet n'etait pas assez chaud, le bordeaux ne devait pas se boire si froid, le biscuit lui occasionnerait certainement une maladie d'estomac...
ストーリー自体は、押川版にあたっていただけば良いかと思うんで、ごく簡単なあらましにとどめる。
飛行船で北極探検に出かけたら恐竜人の地底国がありました。なんだかんだでどうも帰れそうにない、ってことでCeintras/高木が発狂して恐竜人を大虐殺したあげく行方をくらまし、語り手は救出者の訪れを望みつつ探検の記録を書き残す(それが流れ着いて…プロローグにつながる)、ってなとこやろ。
で、実際のところ凄いのは、押川版では完全に省かれているエピローグ部分。ぐちゃぐちゃの手稿を書き起こした後、語り手は、内容を検証するために、飛行船の建造時に二人がいた場所を訪れ、関係者の聞き取り調査をはじめる。そこで明らかにされていく意外な事実…。
ま、そこまで書くのはなんなので、食いついた方は、ブラックコート・プレス版を発注していただきたい。
といいつつ、やはり最後の部分に言及しないではおれないダメな俺。いや、ドレエヌは、ちゃぶ台返ししかけといて、やめちゃうんである。
この時期、飛行船とくりゃあ、「将に来らんとする空中戦争」な訳で、ウエルズのWar in the Airに限らず、未来戦ものといえば飛行船でドンパチなんだが、おそらくそれに対するアンチテーゼとして、人類以外の知的生命とのコンタクトをクローズアップして、国家間の争いの道具としての飛行船から目をそらさせようという構想に力点を置いたとみたね。
しかし、飛行船で北極探検といえば、我々の年代だと『地球頂上の島』なんやが、影響関係はどうなっとるのか(北極探検で恐竜だと『極底探検船ポーラボーラ』)。映画自体については、全く記憶がないので堺さんに、恐竜でてきませんよねえ、と確認してしまいましたよ。ふーん、原作があるのか(The Lost Ones by Ian Cameron/邦訳『呪われた極北の島』評論社)。
でも、原作の年代設定が1960年代だったのを映画化に際して1907年にもってきたとかゆーところを見ると、何かあるぞ。スプラッターな結末部分まで読まないで映画化の企画を進めて、途中で慌てたとか……。さすがにそこまで間抜けなプロデューサーはいない……はずである。